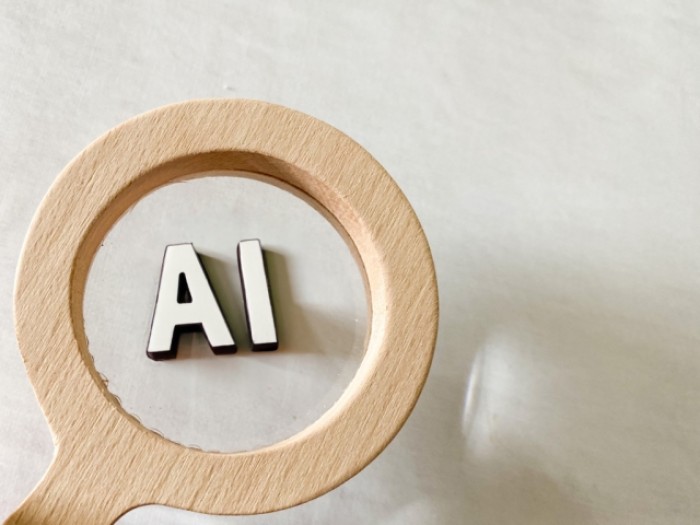弁護士が読む本、読まなくなった本
- INDEX
-
-
1.受験生が読む本は、合格後は読まない
-
2.使わなくなった六法・裁判例集
-
3.基本書と白表紙は覚えるので読まなくなる
-
4.できるだけ薄い本を買ってきて
-
5.ニッチな分野の専門書
-
6.企業法務ではガイドラインをよく使う
-
7.一番読むのは漫画
-
記事提供ライター
-
サイト運営会社:株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社
-
1.受験生が読む本は、合格後は読まない
2.使わなくなった六法・裁判例集
司法試験の問題に適用されるのは最新の法律ですが、実際の事件に適用されるのは、事件が起こった時点の過去の法律です。事件が起こった年の六法を使えば当時の法律がわかります。だから書棚に毎年の六法を並べておくのだと、先輩弁護士たちから教わりました。
判例集は弁護士の生命線です。受験生は、最高裁判所の判例だけを知識として覚えておけば足りますが、弁護士が訴訟を有利に進めるためには、直近の、可能であれば係属中の事件と同じ地方裁判所の、依頼者に有利に引用できる裁判例を探してきて、裁判官に突きつければ、訴訟はかなり有利になります。裁判官は独立しており裁判例に拘束されることはないのですが、同時に、だからこそ、どの裁判官が裁いても同じ結論になるだろうという公平さを重視する裁判官も多いはずです。
六法と裁判例集は弁護士業務に必須です。にもかかわらず、筆者の事務所の書棚には、六法も裁判例集も、受験生時代に用いていた思い出の品しか置かれていません。その理由は、偏にインターネットサービスの充実です。何年何月何日に適用される法律を知りたいと検索すれば、その年度の六法を引っ張り出してくる必要がありません。インターネットサービスならば、書籍化された裁判例集には載らないであろうマニアックな裁判例まで検索できます。世間ではDXやIT化が騒がれていますが、弁護士業界では21世紀初頭からデジタル化が進展し続けており、日々業務が楽になっていくと実感しています。
もっとも、紙に慣れてしまった先輩弁護士は、今でも毎年の六法と、取扱分野の裁判例集を買い集め、法律事務所の図書館化を進めています。お客様の目線になれば、蔵書量が多い法律事務所は立派に見えるはずですから、お客様にもDXやIT化が浸透するまでの過渡的措置としては、先輩方のアナログなやり方が正しいのかも知れません。
3.基本書と白表紙は覚えるので読まなくなる
司法修習では、市場には流通しない、白い表紙の教材が配布されます。これは白表紙(しらびょうし)と呼ばれています。司法修習は実務家を短期育成するプログラムであるため、白表紙には実務で役立つ情報が詰まっています。弁護士稼業に慣れてくると、基本書同様に白表紙の内容は頭の中に刻まれるのですが、未だそこに至っていない新人時代は、白表紙をバイブルのように扱うことになります。
4.できるだけ薄い本を買ってきて
ボス弁も筆者も、その薄い本で仕事ができるとは思っていません。しかし、最低限の業界知識や業界用語を知っておかなければ依頼者との会話が成立しないので、それを効率的に身につけるためには、できるだけ薄い本が好適なのです。依頼者との初回面談は就職活動のようなものですから、業界研究をすることは当然であると、筆者は考えています。
恐ろしいことに、訴訟の相手方弁護士が、目の前の事件の基礎知識を全く理解しておらず、自ら提出した書面の記述について裁判官から質問を受けても、堂々と、専門的なことはわかりませんが、依頼者からそのような説明を受けました、と答えることが多々あります。自分で書いた書面の内容を理解できないような無責任な弁護士にはなりたくないので、筆者はできるだけ薄い本から勉強を始めています。事件の規模によっては、依頼者から勧められた専門家しか読まない分厚い解説書を読み込むこともあります。弁護士は法律だけ学べばよいわけではなく、それが司法試験受験生との最大の違いであるように思えます。
5.ニッチな分野の専門書
6.企業法務ではガイドラインをよく使う
7.一番読むのは漫画
記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。
サイト運営会社:株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社
企業概要>
サービス紹介>
日本のリーガルを牽引する弁護士、法律事務所/企業法務部の姿、次世代を担う弁護士を徹底取材した『Attorney's MAGAZINE』を発行。
『Attorney's MAGAZINE Online』>