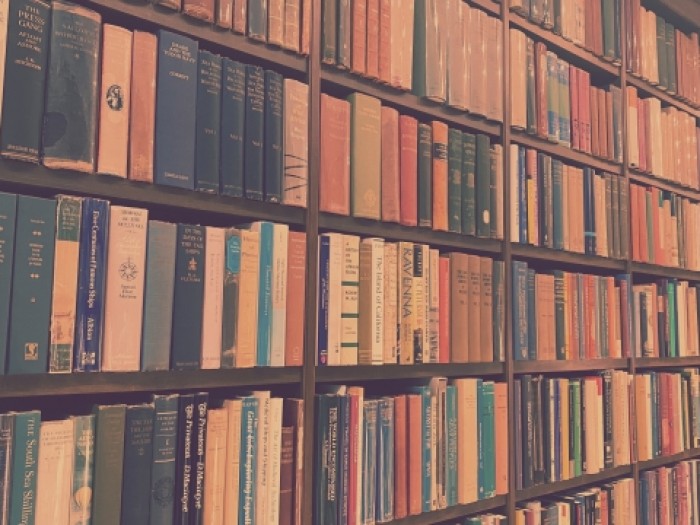現役弁護士が解説!司法試験のデジタル化で何が変わる?
- INDEX
-
-
1.2026年から司法試験がデジタル化?
-
2.弁護士業務とワープロソフト
-
3.手書きの司法試験
-
4.採点者の負担大幅軽減
-
5.課題は専ら運営側にあるか
-
6.弁護士業界の未来は明るい?
-
記事提供ライター
-
サイト運営会社:株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社
-
1.2026年から司法試験がデジタル化?
2.弁護士業務とワープロソフト
ワープロソフトの一番便利な点は、入力後の編集ができることです。カットアンドペーストで容易に順番を入れ替えて、不足があれば書き足すこともできます。筆者が書面を作成する際には、先ず、主張したいこと、書き落としてはならないことを箇条書きにします。そして、どのような順番で主張していけば説得力のあるストーリーができあがるかを考えて並べ替え、アウトラインを作成します。この段階でのアウトラインは、見出しだけのものと、長い文章が混在しています。アウトラインさえできれば、後は肉付けをしていくだけです。裁判書面を作成する際も、契約書を作成する際も、このようなコラムを執筆する際も、作業手順は変わりません。
3.手書きの司法試験
手書きの試験では、弁護士の字は汚くなるし、司法試験考査委員は意味不明な暗号らしきものの解読を強いられるし、それ以前に、書く作業に時間がかかることが問題でした。試験時間の大部分を書く作業に費やすことになる結果、考える力を試されているはずなのに、考えることに割ける時間が短くなり、答案の内容以前に、筆記速度が試される試験になってしまっていました。
書いてしまった答案を編集できないことも問題でした。書く作業に移ってしまうと後戻りができなくなるため、答案構成用紙と呼ばれる白紙を使ってアウトラインを作成し、書き落としてはならない事項をメモしてから、書く作業に移っていました。実務では、書くことが書面作成の第一歩だと言うのに、全く逆の手順です。
書く作業の途中に、あれも書けばよかったこれも書けばよかった、主張の順序を並び替えればより説得力のあるストーリーになった、などと後悔しても後の祭りです。受験生の立場にしてみれば、自分のベストを表現することが許されない受験環境でした。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」にある「受験者の利便性の向上」は、単に手続が簡便になるというだけではなく、書く作業時間を圧縮することで、より考える力が問われるようになり、編集作業が可能となることで、実務家になった後の作業手順で答案を作成できるようになることを意味しています。
4.採点者の負担大幅軽減
5.課題は専ら運営側にあるか
6.弁護士業界の未来は明るい?
弁護士のキャリア形成支援サービス
記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。
サイト運営会社:株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社
企業概要>
サービス紹介>
日本のリーガルを牽引する弁護士、法律事務所/企業法務部の姿、次世代を担う弁護士を徹底取材した『Attorney's MAGAZINE』を発行。
『Attorney's MAGAZINE Online』>