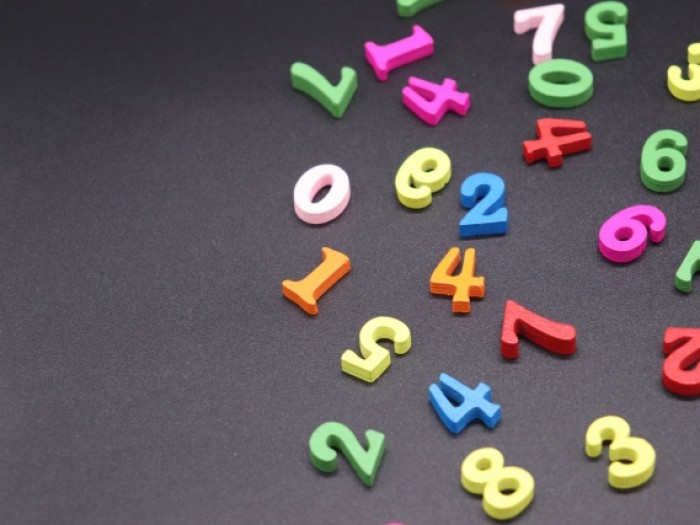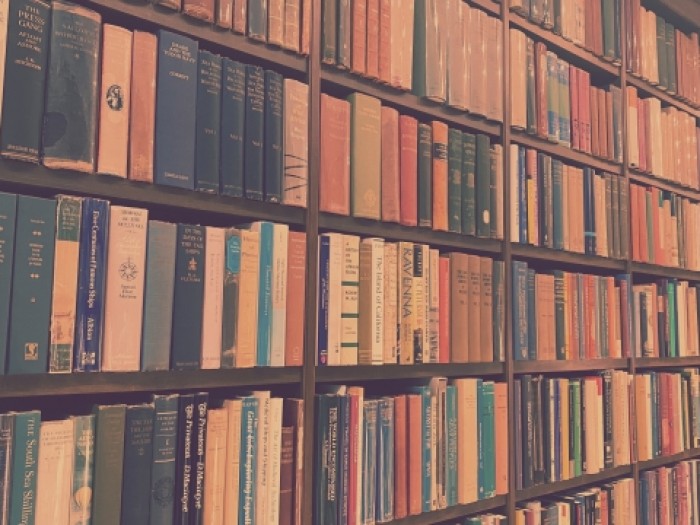AIの発展による弁護士業務への影響
- INDEX
-
-
1.弁護士の仕事がAIに奪われる?
-
2.そもそもAIとは
-
3.AI弁護士の登場と退場
-
4.弁護士の仕事はAIの外にある
-
5.AI利用の注意点
-
6.AIは便利なツール
-
記事提供ライター
-
サイト運営会社:株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社
-
1.弁護士の仕事がAIに奪われる?
2.そもそもAIとは
AIの多くは、ニューラルネットワークという人間の脳の神経網を模した数理モデルに基づいており、これには学習という名の反復計算を延々と繰り返すことで精度を高めていくという特徴があります。ニューラルネットワーク自体は第二次世界大戦中から存在していた古い考え方なのですが、反復計算を何万回と繰り返すためにマシンパワーを必要とし、近年になって、ようやく、必要なマシンパワーが現実的なコストで用意できるようになりました。
3.AI弁護士の登場と退場
AIが法的なアドバイスをすることが禁じられているのは、日本もアメリカも同様です。AIというと、さもSFで登場する人格をもった機械のような響きですが、先のニューラルネットワークについての説明のとおり、人間の脳を模してはいても、本質は計算機に過ぎません。計算機たるAIの人格の主体は、利用者か開発者あるいは運営会社ということになります。そして、AI弁護士においては、運営会社が無資格で弁護士活動を行ったという法的な整理がなされたようです。
日本においても、法務省大臣官房司法法制部が令和 5 年 8 月付「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」(https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf)において、AIを用いた「報酬を得る目的」で「訴訟事件…その他一般の法律事件」または「鑑定…その他の法律事務」についてのサービスは、弁護士に対して提供され、当該弁護士が「自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法で本件サービスを利用するとき」に限って適法になるという見解を示しています。弁護士が責任を取るならばAIを用いても良い、ということです。
弁護士がAIについて責任を負うべき、という考え方に関しては、アメリカ・ニューヨーク州で、弁護士がChatGPTを利用して資料を作成したところ、6件もの実在しない裁判例が引用されてしまい、裁判所から5000ドルの支払いを命じられることになったという事例が参考になります。
4.弁護士の仕事はAIの外にある
実は、この、学習させるデータによってAIの挙動を支配するという構図は、弁護士業務と酷似しています。弁護士は、依頼者に有利になるように事実や証拠を組み立てて裁判所に提出します。裁判官をAIに見立てて、その挙動を支配すべく、学習データを組み立てているとも評価し得るのです。もっとも、裁判官は、AIと異なり、素直に学習データを受け入れるだけでなく、その真偽を見極めるとともに隠されたデータの存在を疑うという、高度な対応をしてきます。弁護士の活動はAI(裁判官)の外にあり、裁判官はAIにはない弁護士(利用者)への疑いを抱けるので、筆者は、現代の枠組みのAIがいくら発展しても、弁護士や裁判官が仕事を奪われることはないと考えています。
5.AI利用の注意点
また、弁護士がAIを用いる際には、守秘義務にも注意する必要があります。具体的な事件についてAIに意見を求めてしまえば、そのAIが他の利用者に対して、弁護士の質問内容に出てきた事件の詳細を明かしてしまう恐れがあります。
その他にも、AIがインターネット上で学習データを集めることが、著作権侵害となりかねない問題もあります。日本国内のサーバー上にあるAIには、日本の著作権法第30条の4第2号が適用されるので、著作物を学習に用いても情報解析目的なので許容される場合が多いと考えられます。しかし、海外のサーバー上にあるAIを利用する際には、現地の著作権にも注意を向けることが求められます。
6.AIは便利なツール
記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。
サイト運営会社:株式会社C&Rリーガル・エージェンシー社
企業概要>
サービス紹介>
日本のリーガルを牽引する弁護士、法律事務所/企業法務部の姿、次世代を担う弁護士を徹底取材した『Attorney's MAGAZINE』を発行。
『Attorney's MAGAZINE Online』>