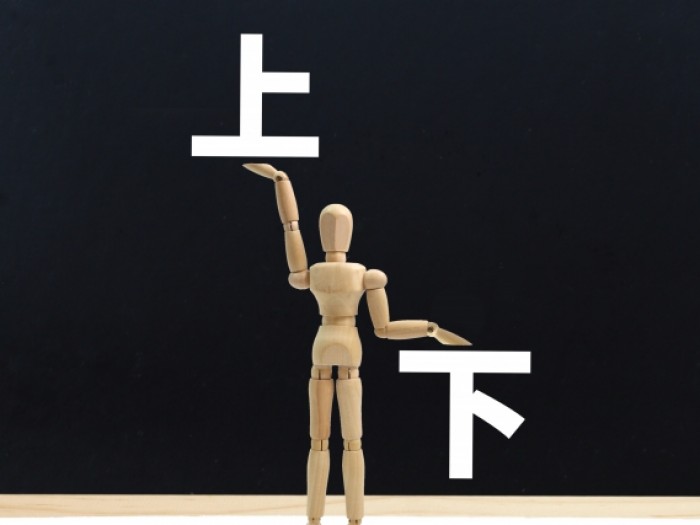弁護士採用難かつ就職難時代のミスマッチ解消策
- INDEX
-
-
1.採用難かつ就職難というミスマッチ
-
2.就職活動の変化
-
3.法律事務所が求人を出す理由
-
4.目立たない求人とミスマッチの発生
-
5.ミスマッチを解消するためには
-
1.採用難かつ就職難というミスマッチ
2.就職活動の変化
しかし、司法試験の合格者数が増加したことにより、人伝(縁故)のみにより法律事務所と司法修習生をマッチングさせることが困難となっていきました。同時期に、拡大志向の法律事務所が積極的に求人を出すようになりました。その結果、新人弁護士の主たる就職の方法は、人伝(縁故)から公募へと大きく変化しました。
筆者は新63期ですが、周囲には、インターネット上で求人を探しては応募する同期もいれば、指導教官や大学・法科大学院の就職課、指導担当弁護士を頼って法律事務所を紹介してもらう同期もいました。集合修習が始まる8月になっても就職先が未定の司法修習生が珍しくなく、先輩弁護士からは、今の司法修習生は就職活動をしなければいけないから大変だと言われていました。就職の方法が人伝(縁故)から公募へと変化していく過渡期でした。
ある法律事務所が、令和3年9月に74期司法修習生を募集したところ、ほとんど反応がなかったそうです。その法律事務所は人気がないわけでは決してありません。実際に、翌月になって75期の採用に切り替えたところ、応募が殺到したとのことでした。74期の司法修習は、2020年2月ごろより発生した新型コロナウイルス禍のため例年より4ヶ月程度後ろ倒しになり、令和4年4月まで続きます。令和3年9月は前半戦が終了するころであり、多くの司法修習生がそれまでに就職を決めているようです。続く75期は、9月に合格発表があったばかりだというのに、司法修習が始まる11月末を待たずに動き始めています。
新人弁護士の就職の方法が人伝(縁故)から公募へと変化するに伴い、就職活動の開始時期も、内定獲得時期も大きく前倒しされている印象です。
3.法律事務所が求人を出す理由
一方で、同統計・調査によれば、法律事務所の大規模化が全体的に進んでいるわけではありません。中小規模の法律事務所が減っていないことについては、こちらのコラムもご覧ください。ここから、中小規模の法律事務所の多くは拡大を志向していないこと、それでも市場から淘汰されていないことが読み取れます。
法律事務所が求人を出す理由は様々です。企業買収や海外での法律調査などのマンパワーを必要とする大型事件に対応できる体制や、より多くの事件を同時に受任できるようにする体制を構築することだけが理由ではありません。弁護士を探している潜在顧客には、法律事務所の経営状態も弁護士の質も知る術はありません。そのため、所属する弁護士の人数が多く、全国に支店を展開している法律事務所が頼れると考える傾向にあります。そのため、法律事務所が所属する、弁護士の人数と支店の数を増やした上で広告を展開すれば、潜在顧客への強い訴えかけが期待できます。仕事を集めるために法律事務所を大きくすることも求人を出す理由になります。
多くの中小規模の法律事務所では、マンパワーを必要とする大規模事件は滅多に発生しません。また、顧問先や過去の依頼者からの紹介だけで仕事を獲得しているため、仕事を集めるために法律事務所を大きくする必要もありません。そんな中小規模の法律事務所が求人を出すのは、仕事が増えるか人が減るかして、紹介のみによって集めた仕事を抱えきれなくなった場合です。このような法律事務所は、余剰人員もいなければ広告費もかかっておらず、財務体質あるいは経営状態は極めて良好です。人の出入りも想定していないため、相性さえ合えば長く働きやすい環境でもあります。筆者には、このような求人は、プラチナ求人とも呼ぶべきものに思えます。
4.目立たない求人とミスマッチの発生
ところが、大規模法律事務所の採用人数の増加と就職活動の早期化により、周囲の司法修習生の多くが大規模法律事務所に就職するようになると、自分だけが中小規模の法律事務所に就職していくことへの抵抗感が生じるのでしょう。また、中小規模の法律事務所は公募に慣れておらず、その魅力を発信することができていないように思えます。そのため、多くの司法修習生が少しでも大きな法律事務所への就職を希望していると聞きます。
また、中小規模の法律事務所が求人を出すのは、現に人手が足りなくなった場合がほとんどです。そのため、できるだけ早くに移籍が可能な経験弁護士か、司法修習終了間近の司法修習生が欲しいと考えます。その結果、司法修習生に対して求人を出す時期は、司法修習生のほとんどが既に内定を得た後になってしまいがちです。
拡大志向ではない中小規模の法律事務所からの求人は、司法修習生の志向の変化、公募への不慣れ、求人を出す時期といった要因が相まって、目立ちません。そのため、なかなか内定を得られずにいる司法修習生も、これに気づくことができず、大規模法律事務所の求人が次の修習期に切り替わっていくことに焦るばかりというのが、現在生じている需給のミスマッチの正体に思えます。
5.ミスマッチを解消するためには
記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。