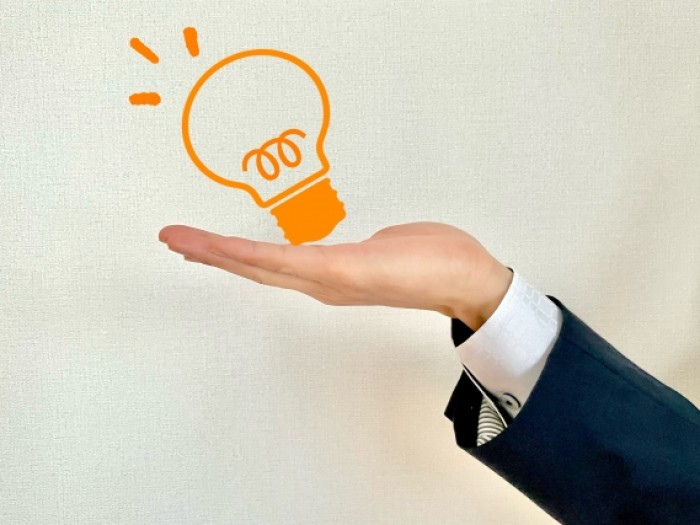ドラマやゲームと現実の違い~異議あり!の使い方~
- INDEX
-
-
1.裁判といえば異議あり?
-
2.民事事件の傍聴は面白くない
-
3.現実の異議あり!
-
4.民事事件は準備が本番
-
1.裁判といえば異議あり?
2.民事事件の傍聴は面白くない
裁判傍聴に詳しい方は、民事事件ではなく刑事事件を傍聴した方が面白いと聞いたことがあるのではないでしょうか。刑事事件は、不安定な地位にある被告人の処遇を早く決する必要があるので、裁判が始まるとスピーディーに手続きが進んでいきます。そのため皆が聞きたがっている異議あり!の登場チャンスも早々に出てきます。
しかし、民事事件では、言いたいことがあるなら書面にまとめて事前提出しろという運用の下、1カ月間隔で交互に書面を出していき、議論が煮詰まったところで、ようやく当事者や証人を呼び出して質問する尋問期日に移ります。当事者や証人が登場するまでに1年以上かかる事件も珍しくありません。裁判官が書面だけからでも判断ができる事件ならば尋問期日がおこなわれないこともあります。民事事件のほとんどの裁判期日では、事前提出した書面の内容確認と、次回作成する書面の内容の指示、次回日程の調整しかおこなわれません。傍聴人は事前に提出された書面を見ることができないので、なにかぼそぼそ話していると思ったら1分程度で終わってしまった、という感想しか残らないでしょう。
3.現実の異議あり!
法律上の異議あり!は、発言者(当事者や証人)の発言内容を糾弾するためのものではありません。質問者(相手方の弁護士)の質問に侮辱や誘導などの問題がある場合に、それを裁判長に指摘して止めさせるためのものです(民事訴訟規則第115条第2項、同第3項、第127条)。異議あり!と言うルールはなく、そもそも異議とは裁判長の判断に対して出すものであって職権発動を促すものではないから、異議あり!というのは間違っているという弁護士もいます。そのためか、裁判長、誘導尋問です、など、異議という単語を使わない弁護士も多いです。他に良い言葉もないので淡々と異議あり!する弁護士もいますが、そのトーンは落ち着いたものです。ドラマやゲームのように発言者を指さしながら異議あり!と叫ぼうものなら、この弁護士は何かそら恐ろしい毒電波を受信してしまったのかと法廷は不安に包まれるでしょう。
異議あり!の言い方だけでなく、出すタイミングも、ドラマと現実とでは全く異なります。当事者や証人には、自ら呼び出した味方と相手方が呼び出した敵方の2種類がいます。そして、それぞれに対する質問は、呼び出した弁護士による主尋問、相手方弁護士による反対尋問、裁判官による補充尋問という順番でおこなわれます。
ドラマやゲームでは、敵方の弁護士が、敵方(敵にとっての味方)に対して主尋問をしているタイミングで、異議あり!その証言は嘘です!と言って証拠をつきつけます。しかし、現実の異議あり!は発言内容ではなく質問方法に対して出されるものであることは先に説明しました。そして、質問者である弁護士はプロなので主尋問のリハーサルをしてから本番に挑んでおり、誘導尋問などの問題のある質問方法を用いずに有利な証言を引き出していくことが大半です。そのため、主尋問には異議あり!される隙はないことが通常です。もっとも、弁護士の準備不足で味方から有利な証言を引き出せず、誘導尋問を繰り返すしかなくなる場合もあります。その場合、先生(裁判長)、弁護士くんがアホな質問の仕方をしています、と言いつけられます。
反対尋問では、敵方の弁護士が呼んできた敵方の当事者や証人に対して、主尋問であなたはこんな証言をしていましたがおかしいですよね、と即興で重箱の隅をつつくことが求められます。そのため、弁護士は、敵方の主尋問において想定されるやり取りに対して、どのように突っ込みを入れるかシミュレーションをして反対尋問に挑みます。しかし、敵方の弁護士も、反対尋問の想定問答集を作ったり圧迫面接のロールプレイをしたり準備してくるので、反対尋問で突っ込もうと用意していた質問は事前につぶされてしまうことが大半です。つまるところ、主尋問も反対尋問も準備合戦であるといえます。まれに、反対尋問において、当事者や証人を侮辱したり執拗に同じ質問を繰り返したりする下品な弁護士がいます。その場合には異議あり!が登場して、裁判長、その弁護士の質問は下品で聞くに堪えないから黙らせてくれ、となります。
4.民事事件は準備が本番
記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。