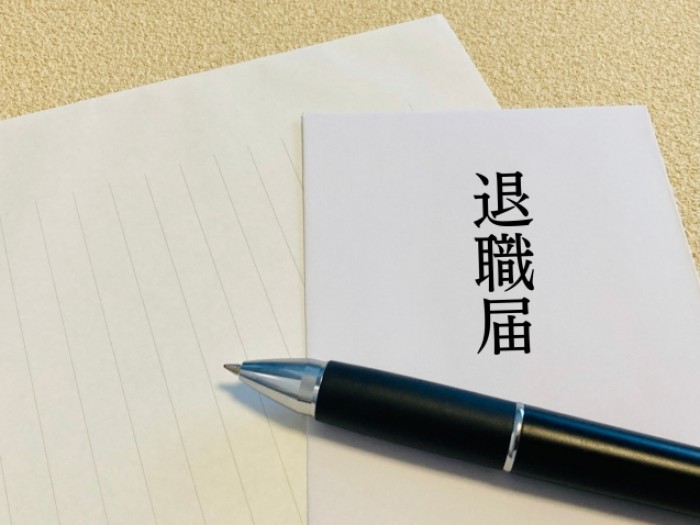企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用するメリットについて
- INDEX
-
-
1.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用する企業が増えている理由
-
2.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用するメリット
-
3.企業内弁護士(インハウスローヤー)の給与はいくら?
-
4.企業内弁護士(インハウスローヤー)の採用方法
-
5.企業内弁護士の採用に失敗しないための注意点
-
6.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用したい企業からよくある質問
-
7.まとめ
-
1.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用する企業が増えている理由
企業内弁護士(インハウスローヤー、インハウスロイヤー)の浸透は若手に限った話ではありません。2011年6月には50期台の企業内弁護士数は208人であったのに、2021年6月には、50期台の企業内弁護士数は446人と倍以上に増えました。これは、多くの企業が、経験を積んだ弁護士を、新たに社内に迎え入れていることを意味しています。
企業内弁護士の人数が増えるに伴い、企業内弁護士の有用性が周知され、企業側の採用意欲が高まっています。ここでは、採用側である企業の視点から、企業内弁護士を採用するメリットや方法、採用の際の注意点などについて解説します。
2.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用するメリット
また、事業分野に関する専門知識や業界慣行を知っているかどうかによって、弁護士によるアドバイスの質は大きく異なります。企業内弁護士は、企業に所属しながら日々の業務をおこなう中で、自然と、事業分野に関する専門知識や業界慣行を身に付けていきます。自社の事業分野に精通した弁護士を自然と育成できることも、企業内弁護士を採用するメリットです。
さらに、弁護士資格を有する従業員が在籍しているという事実は、企業の社会的信用を支えます。企業内弁護士がいる企業ならば遵法意識が高いだろうから信用できる、企業内弁護士を雇える企業体力がある企業だから信用できる、といった信用は無形の財産です。また、弁護士の人数が日本よりも多い国の企業にとっては、法務部門の責任者ならば弁護士資格を持っていて当たり前です。そのような国の企業を取引する際に、企業内弁護士がいなければ、不要な不信感を抱かれてしまいます。これを防ぐことができることも、企業内弁護士を採用するメリットと言えます。
もちろん、企業内弁護士は、契約書の作成や添削、日常的な法律相談といった企業の法務部門に求められる能力においても、高い資質を有しています。単純に優秀な法務部員を雇いたいという場合にも、企業内弁護士の採用は有力な選択肢になるでしょう。
日常的に業務の一部を企業の外の弁護士に外注している企業にとっては、その業務を内製化することでコスト削減も期待できます。企業の外の弁護士に訴訟事件を依頼する際にも、企業内弁護士がいれば、必要な証拠や資料を整理して状況を的確に説明できますから、事件を有利に進めることが可能になります。
3.企業内弁護士(インハウスローヤー)の給与はいくら?
年齢層毎に見ると、34歳以下では「700万円未満」が51.2%、35~39歳では「700~900万円未満」が30.4%、40~49歳では「900~1,100万円未満」が27.9%、50歳以上は「2,000万円以上」が39.6%でそれぞれ最多回答となっており、年齢に応じて年収も上昇していくことがわかります。もっとも、当然のことながら、同じ年齢の企業内弁護士であっても、企業内でのポジションや経歴によって年収は大きく異なるので、一概にいくらが相場ということはできません。
4.企業内弁護士(インハウスローヤー)の採用方法
上で触れた日本弁護士連合会による第3回「企業内弁護士キャリアパス調査」に関する調査(2021年3月~5月実施)の回答結果 Q20:企業内弁護士が就職活動の際に役に立ったものにおいて、複数回答合計450のうち、就職エージェントの紹介を受けた265、友人、先輩、他の弁護士などの紹介を受けた83、勤務先企業のホームページや資料請求をして情報収集した81、日弁連の「ひまわり求人求職ナビ」を見て応募した76、弁護士会主催の就職説明会に参加した50が目立ちます。
アンケート結果から、採用側の企業としては、就職/転職エージェントを利用することが最も効率よく企業内弁護士(インハウスローヤー)を志向する弁護士にアクセスする方法となることがわかりました。ひまわり求人求職ナビを利用すること、弁護士会主催の就職説明会に参加すること、も有益です。また、既に企業内弁護士(インハウスローヤー)がいる場合には、その友人や後輩に直接アプローチすることも効果的な採用方法となります。
5.企業内弁護士の採用に失敗しないための注意点
また、弁護士が資格を維持するためには弁護士会費の納付が必要となります。弁護士会費は登録している弁護士会によって異なるのですが、毎月数万円以上という大きな金額です。日本組織内弁護士協会による企業内弁護士に関するアンケート調査集計結果(2021年3月実施)によると、企業内弁護士のうち86%は、弁護士会費を企業が負担しています。自ら弁護士業務を営むわけではない企業内弁護士にとって、弁護士資格は所属する企業における業務に役立てるために維持するものですから、そのための費用は所属する企業が負担するというのは不合理な話ではありません。
さらに、弁護士は、所属する弁護士会から、委員会活動への参加や国選弁護事件などの公益活動が義務付けられています。企業内弁護士を採用する際には、勤務時間中に委員会出席や刑事事件への対応が生じてしまう場合があることにも注意が必要です。
その他、弁護士は万能ではないと知ることも必要です。一口に弁護士といっても経験やスキルは千差万別で、裁判が得意な弁護士もいれば、契約書の作成が得意な弁護士もいます。採用の際には、その弁護士が真に求める能力を有しているかを吟味する必要があります。
6.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用したい企業からよくある質問
Q1.弁護士会費は企業と企業内弁護士(インハウスローヤー)のどちらが負担するのですか?
Q2.企業内弁護士(インハウスローヤー)は必ず弁護士登録をする必要はあるのですか?
Q3.企業内弁護士(インハウスローヤー)を採用しやすい時期ありますか?
Q4.企業内弁護士(インハウスローヤー)に訴訟代理人を任せても良いですか?
Q5.企業内弁護士(インハウスローヤー)がいれば顧問弁護士は不要ですか?
Q6.企業内弁護士(インハウスローヤー)を公益活動に参加させる義務はありますか?
Q7.副業(個人受任)を許可する必要はありますか?
7.まとめ
記事提供ライター
大学院で経営学を専攻した後、法科大学院を経て司法試験合格。勤務弁護士、国会議員秘書、インハウスを経て、現在は東京都内で独立開業。一般民事、刑事、労働から知財、M&Aまで幅広い事件の取り扱い経験がある。弁護士会の多重会務者でもある。